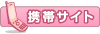公開日 2024年06月13日
勝浦町不妊治療応援事業
勝浦町では令和6年度から、子どもを望むご夫婦が不妊治療を受けた際の経済的な負担を軽減するため、保険診療で実施された生殖補助医療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療にかかった費用の一部を助成しています。
令和7年度からは、さらなる支援として助成上限額を5万から10万円に増額します。(ただし、治療開始が令和7年4月1日以降の治療からが対象です)
下記の助成額をご確認ください。
助成の申請ができる方(次の①~⑥のすべてに該当する方)
①法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であること。
②助成申請をした日において、夫婦ともに1年以上継続して勝浦町の住民基本台帳に記録されていること。
③助成申請に係る治療の期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
④助成申請に係る治療について、他の自治体等が実施する治療の助成を受けていないこと。
⑤ 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されたこと。
⑥本事業の助成の申請日において、夫婦及び当該夫婦の属する世帯の全員が町税等(勝浦町)の滞納がないこと。
助成対象となる治療
令和6年4月1日以降に保険診療で実施された生殖補助医療及びその一環としての男性不妊治療(精巣内精子採取術等)。
助成対象範囲は、こちら→ 助成対象範囲[PDF:277KB] をご確認ください。
助成額
上記の助成対象となる治療に要した自己負担額の合計金額に相当する額とし、治療開始が令和7年4月1日以降の場合は、1回あたり10万円を限度に助成します。
※治療開始日が令和6年度中である場合は、1回あたり5万円を限度とします。
ただし、自己負担額に対し、医療保険各法等の保険者が負担すべき高額療養費及び保険者からの付加給付がある場合は、これを控除するものとします。
※入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
【助成上限額の考え方】
例:治療期間が令和7年3月17日~令和7年4月11日の場合⇒治療開始が令和6年度中のため助成上限額は5万円
例:治療期間が令和7年4月1日~令和7年4月11日の場合⇒治療開始が令和7年度のため助成上限額は10万円
助成回数(保険適用回数にあわせています)
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が
40歳未満の方:子ども一人あたり通算6回まで
40歳以上43歳未満の方:子ども一人あたり通算3回まで
この場合において、以前に実施した体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
助成の申請
1回の治療計画による助成対象診療が終了した日から1年以内に、次の必要書類を福祉課に提出してください。
①~④、⑧の様式は、福祉課窓口で受け取っていただくか、ダウンロードしてご使用ください。
①勝浦町不妊治療応援事業申請書(様式第1号)
令和6年度中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に開始した治療にかかった費用の助成申請はこちらの様式⇒様式第1号[PDF:93.7KB]
令和7年4月1日以降に開始した治療にかかった費用の助成申請はこちらの様式⇒(治療開始が令和7年4月1日以降)様式第1号[PDF:94.1KB]
②勝浦町不妊治療応援事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書(様式第2号)※印刷する際は両面印刷してください
様式第2号[PDF:269KB] ※医療機関に様式を渡して証明書を作成してもらってください。
③町税等調査閲覧同意書(様式第3号)様式第3号[PDF:87.3KB]
④高額療養費等の照会に伴う同意書(様式第4号)様式第4号[PDF:56.9KB]
⑤医療機関等が発行する助成対象診療に要した費用の領収書及び診療明細書(院外処方分含む)
⑥保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等 ※高額療養費の支給申請については加入している医療保険者にお問い合わせください。
高額療養費制度についてはこちら→高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省 (mhlw.go.jp) をご参照ください。
⑦戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。
ア 初めて本事業の申請を行う場合
イ 夫婦が別世帯の場合
ウ 夫婦が事実婚関係にある場合
⑧ 事実婚関係に関する申立書(様式第5号)※事実婚関係にある場合のみ必要様式第5号[PDF:56KB]
⑨「限度額適用認定証」または「限度額適 用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はご持参ください。
⑩助成金の振込先となる申請者名義の通帳をご持参ください。
※必要書類をご用意していただく際に生じた費用は自己負担となります。
助成の決定
必要書類がすべてそろってから審査します。
審査結果は、勝浦町不妊治療応援事業助成金交付(不交付)決定通知書により通知します。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード